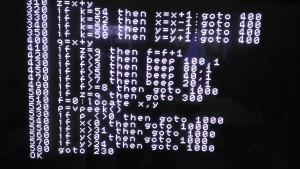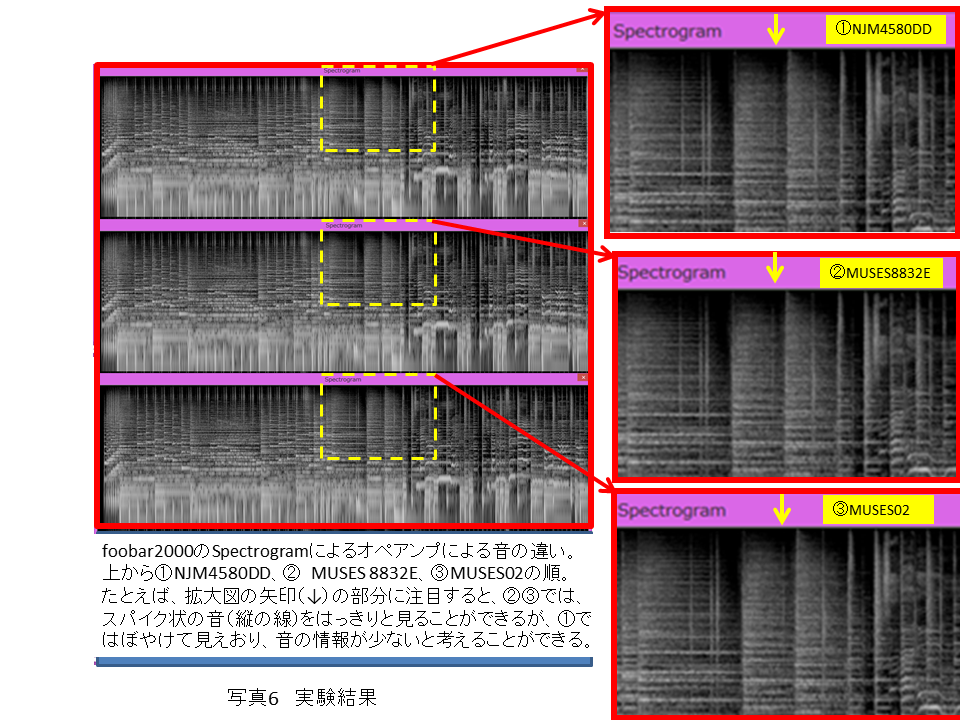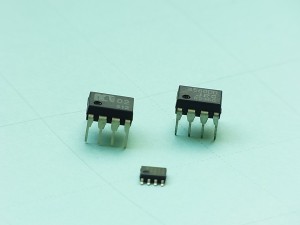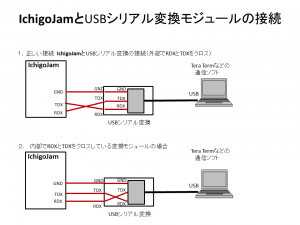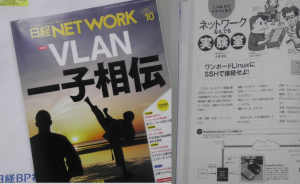日経NETWORK 2015年11月号 発売
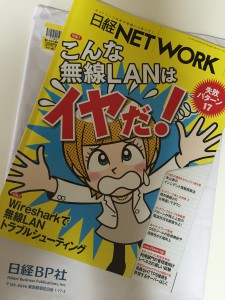
今月号は、連載記事の「ネットワーク実験室」に加え、 特集2「Wiresharkで無線LANトラブルシューティング」を担当しました。 最近は、スマホやタブレットの普及で、無線LANのトラブルシューティングの機会が増えているかと思います。有線LANのパケットキャプチャでは、オープンソースのWiresharkが有名ですね。Wiresharkでも、 無線LANのパケットのキャプチャができます。 特に、無線LANの場合、電波状況やIEEE802.11無線LANフレームなど低いレイヤの情報が必要になることも多いです。 しかし、Windows版のWiresharkの場合、特殊なアダプタを使わないと、IEEE802.11フレームそのままの姿でキャプチャすることができません。 そこで、linux版のWiresharkを使うと、条件はありますが、IEEE802.11フレームやラジオタップヘッダと呼ぶ無線の情報をキャプチャすることができます。 この特集では、Wiresharkを使った無線LANのキャプチャの方法や、Windows版とlinux版のWiresharkの違い、Wiresharkを使った無線LANのトラシュー事例などを書いています。 連載の「ネットワーク実験室」は 「ドローンが飛ぶ上空の電波状況を調査せよ!」です なにかと話題のドローン(空飛ぶマルチコプター)の中には、2.4Ghz帯ISMバンドの無線LANを使って機体のコントロールをしたり、動画の無線伝送を行うタイプがあります。しかし、街中では、建物内外の無線LANのAP(アクセスポイント)が山ほどあり、それが2.4Ghz帯ISMバンドの混雑の一因となっています。そこで、上空のドローンから、2.4Ghz帯の無線LANを見ると、地上のAPがどれほど、検知できるのか、実験してみ…たかったのですが、9月の法改正で、街中でドローンを飛ばすことはできなくなりました。そこで、代わりに高いところ、高いビルの展望台から、無線LANのツールを使って、無線LANのAPの数や電波の強さを調べました。はたしてその結果は…

日経ネットワークhttp://itpro.nikkeibp.co.jp/NNW/ は 、大きな本屋さんで店売しているところもあります。 見かけたら、手に取って頂ければ、幸いです。